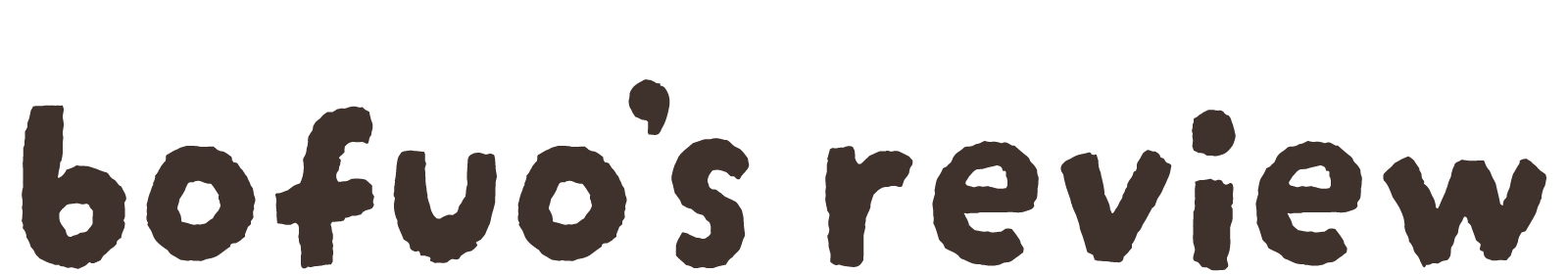マルク・レビンソンの『コンテナ物語』は、海上輸送で使われるコンテナが発明され、世界に普及するまでの歴史を描いた本です。

コンテナ導入の技術的な側面だけでなく、海運会社と競合する鉄道やトラック、自治体による港湾の整備、旧来の港湾労働者による抵抗活動など、業界を取り巻く状況が詳しく描かれています。
またベトナム戦争やオイルショックなど、当時の社会情勢がグローバリゼーションに及ぼした影響にも言及されていて、歴史書や経済学の本としても読めます。
物流業界とは関係のないビジネスパーソンでも、コンテナ普及の立役者マルコム・マクリーンの会社経営ノウハウは参考になると思います。
本記事のリンクには広告が含まれています。
グローバリゼーションの条件
「海外で生産された輸入品を、100円やそこらで販売して元がとれるはずがない」と不思議に思いませんか?
私たちが普段、ダイソーやユニクロで信じられない低価格の雑貨や衣料を買える背景には、コンテナ革命による輸送コストの低下が影響しています。
家具や家電といった大型生活用品も同様で、イケアのフラットパックなどはコンテナに入れたまま、港から各店舗に配送されているそうです。
生産拠点を土地と人件費の安い国に分散させること、つまりサプライチェーンのグローバル化にとって、コンテナによる輸送費の大幅低減は必須条件だったとされています。
コンテナの登場で、モノの輸送は大幅に安くなった。そしてこのことが、世界の経済を変えたのである。
マルク・レビンソン『コンテナ物語』(以下同)
まるでジャレド・ダイヤモンドの『銃・病原菌・鉄』で描かれているように、ヨーロッパ諸国がアメリカ大陸を征服できた背景には、目に見えない伝染病の影響があった(ヨーロッパ人だけ免疫を持っていた)と聞くようなインパクトがあります。
普段は意識することのないコンテナおよび物流システムが、実は身のまわりにある消費財の低価格化を後押ししていたと知って驚きました。

倉庫としても使われるコンテナ
たかが箱、されど箱
英語の原題『THE BOX』という短いタイトルには、「単なる箱」「たかが箱」という皮肉が込められているように感じます。

これまでは「あまりに凡庸で退屈な代物」「単純すぎて研究対象に値しない」と見なされていたコンテナ業界を、徹底的にリサーチしたのが著者マルク・レビンソンの功績です。
20世紀の半ば以降、経済や貿易に影響を与えた要因はあまりに多く、その陰でコンテナの存在はずっと無視されてきた。誕生から半世紀が過ぎたというのに、コンテナの歴史を描いた本は一冊もないのである。
見た目はそっけないコンテナが、実はグローバリゼーションに不可欠な要素だったというのがこの本の主張です。
歴史を振り返ってみれば、モノを入れて運ぶ単なる金属の箱が、車輪の発明に匹敵する破壊的イノベーションだったのかもしれません。
そういった意味ではコンテナという物理的な箱よりも、輸送システム全体を指して「コンテナリゼーション」と呼んだがほうが適切かと思います。
標準的なコンテナは空き缶と同じで、ロマンのかけらもない。この実用的な物体の価値は、そのモノ自体にあるのではなく、その使われ方にある。さまざまな経路と手段を介して最小限のコストで貨物を運ぶ高度に自動化されたシステム。その主役が、コンテナである。
とはいえコンテナについて書かれた本など、誰もが読みたくなるような興味深い代物ではありません。
かくいう自分も10年以上、Amazonの「ほしい物リスト」に入れっぱなしでした。
気づけば『コンテナ物語』は版を重ねて、2019年には増補改訂版が出ているベストセラーに…
よくわからないですが、こういうニッチなテーマに興味を覚える読者もいるようです。
楽天市場のセールで還元ポイントを増やすためついでに注文して、ようやく読むことができました。
海運業界の5フォース
『コンテナ物語』に登場する面々は、マイケル・ポーターの5フォースに整理することができます。
- 業界内の競合…新旧海運業者間の競争、M&A
- 売り手の脅威…造船会社、港湾当局、港湾労働者などとの協力・対決
- 買い手の脅威…荷主からの交渉(値下げ)圧力
- 代替品の脅威…鉄道、トラック輸送
- 新規参入者の脅威…米国以外、次世代の海運会社
戦後のアメリカ海運業界は、州際交通委員会(ICC)の規制で新規参入が制限され、船会社の同盟というカルテルが一律運賃を定める硬直化した世界だったようです。
そこに元トラック野郎のマルコム・マクリーンという起業家がコンテナを発明して価格破壊を引き起こし、競合他社からの妨害や他業界からの圧力にも負けずに事業を成功させた……とまとめればわかりやすいのですが、実際はそうすんなりと行かなかったことが明らかになります。
コンテナ以前
MacやiPhoneはスティーブ・ジョブズがひとりで開発したものではないとわかっていても、読者は発明家や起業家といったヒーローを求めるものです。
著者はコンテナの発明をマクリーンひとりの業績に仕立てる意図はなく、「技術の進化は複雑なプロセスであり、一人の人間の英雄的な努力だけでやり遂げられることはめったにない」と冒頭で書いています。
そもそもマクリーンがシーランドを創業してコンテナ事業を始める1950年代より以前に、「コンテナらしきもの」は鉄道業界で19世紀後半から導入されていたそうです。
すでに1920年代にはアメリカ以外の鉄道にもコンテナが広がって、1933年に国際コンテナ協会(ICB)が発足していました。
米軍もコネックス・ボックスと呼ばれる小型のコンテナを導入しています。
ただ初期のコンテナはサイズが小さく木製でフタもなかったため、たいして効率的でなかったようです。
容器が小さいとかえって重量がかさむだけで、しかも空のコンテナにも関税がかけられたということから、劇的なコスト削減には結びつかなかったと説明されています。
コンテナのメリットを最大限に生かすには、サイズを大きくしてクレーンや船も専用のものを用意し、導入・運用コストを輸送効率が上まわるような、損益分岐点を超える必要があったのでしょう。
マーケティングの発想
海運業界に対するマルコム・マクリーンの貢献とは、米国初のLBO(レバレッジド・バイアウト)や借入を駆使して莫大な資金を集め、コンテナの大型化と流通のシステム化に先行投資したという点にあると思います。
そして陸路も含めたインターモーダル(複合一貫)輸送を構想したということが、当時は斬新なアイデアだったようです。
マルコム・マクリーンがすぐれて先見的だったのは、海運業とは船を運航する産業ではなく貨物を運ぶ産業だと見抜いたことである。
つまりマーケティングに関してセオドア・レビットが言っているように、顧客が欲しいのはドリル(コンテナ)ではなく穴(輸送コストの削減)という、消費者側の視点を海運業界に持ち込んだ点を著者も評価しています。
規制や同盟に保護されていた船会社出身ではなく、トラック運送会社からキャリアを始めたことで、柔軟な発想ができたのかもしれません。
もしマクリーンが今の時代に生きていたら、コンテナも運べる大型ドローンを内陸部への貨物輸送に導入していたのではないかと想像します。
誰もが失敗した業界
しかしマルコム・マクリーンも晩年の活動はほとんど的外れだったそうです。
1973年オイルショックの直前に燃費の悪い高速船SL7を発注し、さらに原油価格が急落した頃に低速のエコノシップを世界一周航路に投入したことで、会社倒産の原因をつくっています。
どちらも原油価格の変動に対して、導入のタイミングが悪すぎたという理由です。
自治体の港湾整備に関する投資も、コンテナ普及期には軍拡競争のようになり、地理的条件に恵まれた港以外は報われなかったようです。
特にアメリカのニュージャージーに対するニューヨークの没落ぶりが詳しく描かれています。
「マクリーン自身も、何度も選択を誤った」
「市場も国も何度もまちがいを犯し、民間部門も政府部門も何度も判断を誤った」
と著者が終章でまとめているとおり、コンテナ業界で最初から最後まで大成功したヒーローはいなかったようです。
むしろ造船も港湾整備も規格策定も何もかも失敗続きだったのに、しぶとく改善を続けられたコンテナが長年かけてようやく普及した、というのが実情と思われます。

今は観光地と化したサンフランシスコの埠頭(ピア39)
橘玲さんが「構造的な問題はいずれ現実化する」と言っていますが、コンテナはその逆だったみたいです。
技術的・政治的な障害にはばまれつつも、合理的な方式であることは誰にも明らかだったため、不可逆的に浸透していくストーリーのように見えました。
映画『シン・ゴジラ』に「完璧ではないが、最善を尽くしている」というセリフが出てきます。
コンテナの標準化に関する各業界の取り組みも、泥臭い交渉や改善の積み重ねだったように思われます。
沖仲仕という仕事
海運業界を取り巻くサプライチェーンの一要素として、港湾労働者すなわち沖仲仕(おきなかし)という仕事が取り上げられています。
『コンテナ物語』では沖仲仕の漢字にルビが振られていなかったため、最初はなんと読んでいいのかわかりませんでした。
コンテナが導入される以前、船に積まれた荷物を積み下ろしするのはクレーンと人力に頼っていて、たいへんな肉体労働であったようです。
ここでモノを言うのは筋肉だけである
沖仲仕は日雇いで収入が不安定ですが、身一つで参入できるため従事する人数も多く、当時は一大産業だったと描かれています。
過酷な労働という港湾労働の特殊性から、波止場には独特の文化が生まれ、排他的な労働組合が結成されていました。
沖仲仕の賃金が海運コストの半分を占め、さらにストライキも頻発する状況から、コンテナの登場および費用削減は自然な流れだったと考えることもできます。
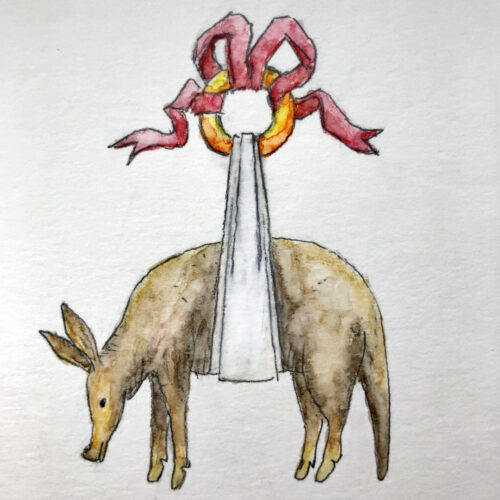
ブルックス・ブラザーズ
今は港で荷物を運ぶ集団などいなくなり、沖仲仕は映画や小説といったフィクションのなかでしか見かけない職業といえます。
『コンテナ物語』では当時を知る手がかりとして、マーロン・ブランドが出演した『波止場』という1954年の古い映画を紹介しています。
自分は昔読んだアンドレ・マルローの『征服者』という小説を思い出しました。
≪広東(カントン)でゼネスト指令≫
という見出しで始まる、中国の五・三〇事件を題材にしたマルローの小説も、港湾労働者のストライキを取り上げています。
1964年初版の中央公論社「世界の文学41」に収められた『征服者』を読み返すと、沖仲仕(おきなかし)と漢字に振り仮名がつけられていました。
同作品に登場する苦力(クーリー)と同じく、この頃には日本でもすでに沖仲仕が死語となりつつあったのかもしれません。
海上労働者の共通点
ちなみに沖仲仕のビジュアルなイメージでいうと、漫画のポパイ(Popeye)が近いかと思ったのですが、彼は港湾労働者ではなく水兵(船乗り)でした。
水兵といえば『沈黙の艦隊』や『空母いぶき』といった自衛隊をテーマにしたマンガでも、「シーマンシップ」「サブマリナーの誇り」といった精神論がさかんに登場します。
外的条件の厳しい海上で長期間、団体行動をとる必要性から、船乗りにも沖仲仕と同じく、特殊な忠誠心や連帯感が生まれやすいのかもしれません。
つまり港で働くということは、全世界どこでも同じタフガイ・クラブの仲間入りをすることにほかならない。
港湾労働者ではなく漁夫のストーリーですが、小林多喜二の『蟹工船』も虐げられた出稼ぎ労働者が団結してストライキを起こすという物語でした。
きつい仕事とはいえ荷役は共同作業で、仲間内でのコミュニケーションは濃密になるため、精神的には案外楽しい職業だったのかもしれません。
また労働組合の力が強かったせいか、沖仲仕はほかの平均的な肉体労働者より実入りはよかったらしいです。
規格と標準化
『コンテナ物語』の醍醐味のひとつとして、規格化に関する経緯を取り上げてみたいと思います。
コンテナ黎明期は米国で30種類以上の規格があり、各会社や陸軍で扱うユニットに互換性はなかったそうです。
将来予想される混乱を避けるため、米海事管理局(MARAD)や米国規格協会(ASA)、さらに国防輸送協会(NDTA)といった団体がコンテナ規格の統一に乗り出します。
それ以前に統一されていた鉄道のゲージに比べて、コンテナの規格は関わる業界が船・鉄道・トラックと多岐にわたるため、意見の調整が難しかったようです。
米国内でもめた末、最終的に国際標準化機構(ISO)が「幅/高さ8フィート、長さ10、20、30、40フィート」という切りのよい数字でコンテナサイズを策定します。
ところがこれも市場ではいまいち不評だったとのこと。
パンアトランティック海運とマトソン海運という、当時の2大コンテナ輸送業者が採用しているサイズも、ISOの定める規格とは異なっていたからです。
- パンアトランティックの35フィートは母港のニュージャージーに向かうハイウェイで許可される最大サイズ
- マトソンの24フィートは同社の主要貨物であるパイナップル缶を運ぶのに適したサイズ
それぞれ一応、採用にいたった合理的な理由はありますが、他国の運送業者にとってはどうでもいい話です。
最終的に、多大な投資が必要になるコンテナ船の建造において、「国の規格に合わせないと補助金をもらえない」という事情が規格の決定を左右したようです。
結局、大手2社もそれまでの投資が無駄になることを承知で、ISO規格に従うほうを選びました。
QWERTY配列の例
話が変わってパソコン用キーボードの世界では、タイプライターの時代に開発されたQWERTY配列が主流になっています。
- タイプライターの故障を防ぐため、わざと打鍵速度を落とす
- 他社製品への乗り換えを防ぐため、わざと覚えにくい配列にする
というコンセプトで導入されたといわれるQWERTY。
不便なはずなのに、なぜか現代のパソコンでも採用され続けています。

人間工学の観点では、DvorakやKALQという指の移動距離が短くて済むキー配列も考案されています。
「早打ちできて疲れにくい」という点では圧倒的にQWERTYより有利なはずですが、こうした配列のキーボード製品をお店で見かけることはまずありません。
この分野では、先に普及してユーザーが慣れてしまった配列・規格のほうが強かったのではないかと思われます。
QWERTYの例から連想して、コンテナにおいても人為的に定められたISO規格より、実績ある大手海運会社の規格が定着しそうな予感はしたのですが、実際はそうなりませんでした。
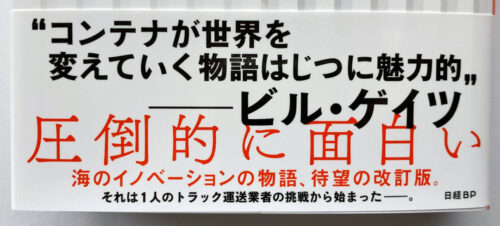
コンピュータと通信分野においても「規格の標準化」というのは重要なテーマです。
『コンテナ物語』の帯にはビル・ゲイツが「圧倒的に面白い」とコメントを寄せています。
元マイクロソフト日本法人社長の成毛眞さんも『コンテナ物語』を絶賛していました。
IT大手の経営者にとって、コンテナ規格の論争には共感するところが多いのかもしれません。
コンテナと似たパケット
さらに余談ですが、海運業界をIT業界、物流を通信に置き換えると、コンテナと似たようなものに「パケット」という概念があります。
元は米国防省が開発したアーパネット(インターネットの前身)で採用された軍事技術ですが、データを小分けにして分散送信することで、細い回線でも安定して通信できるという工夫です。
パケットという規格と、TCP/IPのようなプロトコルがセットで運用されることで、情報通信の分野においてもコンテナリゼーションのような効率化を実現できたと考えられます。
パケット交換が発明されたのは、コンテナ普及期と同じ1960年代でした。
「規格化されたユニットに荷物(データ)を収めて扱いやすくする」という発想は、コンテナとパケットでよく似ています。
『コンテナ物語』では言及されていなかったですが、もしかすると通信技術のパケットという概念が物流革命に影響を与えたかもしれません。
あるいはその逆に、「コンテナを見た通信技術者がパケットをひらめいた」というエピソードもあったりしそうです。
ハイリスクな規模の経済
ITや一般的な製造業と比べたコンテナリゼーションの難しさは、最初に多大な投資が必要という点にあります。
コンテナ輸送サービスというものは、スタートするその瞬間から大規模にやらなければならない
…(中略)…
巨額の資本を一気に投じて十分な数の船とコンテナをそろえ、大型港を結ぶ定期航路に高頻度のサービスを実現しないと勝ち目はない
まさに「規模の経済」が成り立つ、典型的な業界です。
コンテナ輸送が意味するのは、ただ「金属の箱で物を運ぶ」というだけではありません。
コンテナを効率的に積み下ろしできる船やクレーンの開発から、船舶の運航をコンピューターで効率的に管理するところまで、すべての要素が整ってはじめて最大限の効率を発揮するシステムです。
船会社の資本力で港をつくれるわけはなく、政府や港湾当局が協調する必要があり、さらには荷物を預ける顧客企業も、コンテナの効率的な使い方を学習する必要があったといえます。
歴史的な経緯としては、ベトナム戦争で米軍のロジスティクスに採用された実績も大きかったようです。

六甲山から見た神戸のコンテナ港(六甲アイランド)
それなりに優秀な技術者や政治家が、めいめいの思惑でコンテナ導入を推進してきたとはいえ、結局行き当たりばったりで何とか取り繕いながら普及して経緯が想像できます。
「専門家や先駆者でさえ繰り返し予想を誤った」と書かれているように、コンテナ業界はプレーヤーが多すぎる複雑系で、株式市場のように予測は難しかったと思われます。
コンテナの教訓
『コンテナ物語』から何か会社経営の教訓みたいなものを学べるとしたら、それは著者も書いているとおり「予想外のことにそなえる」ということに尽きます。
1950年代にコンテナ輸送のサービスが始まったときは、せいぜい沿岸航路に使えるニッチな技術で、外洋航路や輸出入には使えないと考えられていたそうです。
今の技術でたとえれば、岐阜県飛騨地域で使われている「さるぼぼコイン」みたいな地域通貨が、なぜか50年後にドルやビットコインを追いやって世界の基軸通貨になってしまったくらいのインパクトでしょうか。
さらにコンテナ輸送に参入するには多大な投資が必要なうえ、早すぎても遅すぎてもダメという「タイミング」が重要だったと考えられます。
コンテナがブームとなった1970年前後に、一時は参入業者が多すぎて供給過剰になり、値下げ競争におちいったすえ業界再編が行われています。
規模の経済なので先行投資が有利とはいえ、規格策定の行方や顧客ニーズを見極めてから参入した後発組のほうが、今ではうまくいっているように見えます。
コンテナ業界の立役者、マクリーン・インダストリーズも1986年に倒産して、現在はイタリアのMCS、デンマークのマースクといった米国以外の欧州企業が海運業界を支配しています。
中国のCOSMOや台湾のエバーグリーンといったアジア勢も、コンテナ船積載量ランキングの上位を占めています。

広島で見かけた商船三井MOLのORCA ACE(コンテナ船ではなく自動車船ですが)
未知の未知に備える
歴史を振り返ってみると、コンテナの出現はブラックスワンだったのでしょうか?
船会社や港湾局の死屍累々たるチャレンジの末に、誰にも予想不能かつコントロールできないかたちで最適化されたのが今のコンテナ・エコシステムなのかもしれません。
その過程で、混載貨物の船や港湾労働者はほとんど姿を消しました。
われわれ一般庶民ができることとしては、「将来AIに仕事を奪われそうな、沖仲仕と似た単純作業の業種はなるべく避ける」ということくらいでしょう。
とはいえ現代のコンテナ港で花形といえそうなガントリークレーンのオペレーターでさえも、いずれ運用が自動化されればお払い箱になりそうです。
経営側を目指すとしても、博打が外れて歴史に名を残せなかったコンテナ事業者はごまんといたはずです。
天才的な起業家だったマルコム・マクリーンも、結局最後まで業界に残り続けることはできませんでした。
「50年後も稼げる仕事」といった予測不能なことを予測しようとがんばるよりは、おとなしく「さるぼぼコイン」でベーシックインカムをもらえる未来を想像したほうがましかもしれません。
『コンテナ物語』増補改訂版のぶ厚い449ページ(うち66ページは原注と参考文献リスト)を読み終えて、「規格化ビジネスは運がすべて」とでもいうような無力感を覚えました。