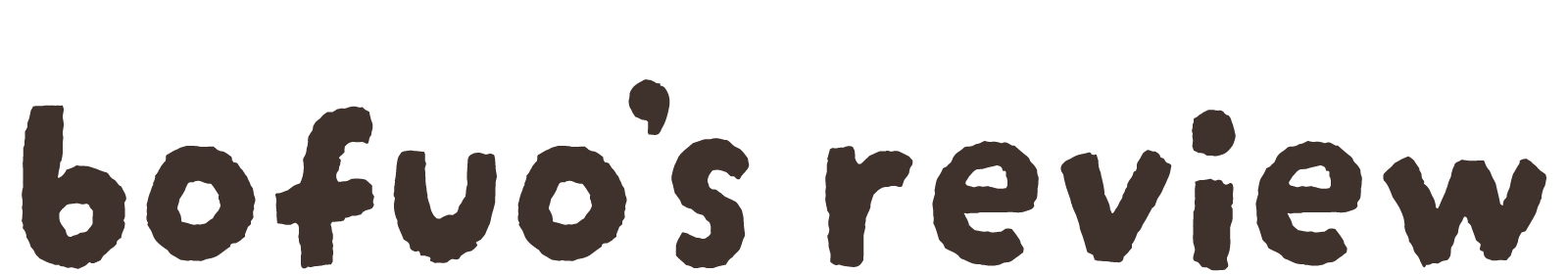ジョン・ケネス・ガルブレイスの『新版 バブルの物語』は、歴史上の投機バブルに共通するパターンと、そこから引き出される教訓を教えてくれる本です。

2024年初頭は日経平均が1989年バブル後の最高値を更新し、AI関連銘柄やビットコインが急騰しています。
米国の利下げを予測してさらなる株高を期待する意見がある一方、久々のバブル到来を危惧する警告も聞かれます。
今が買い時か売り時か悩んでいる方は、この本を読めば冷静な判断を下せるようになるかもしれません。
本記事のリンクには広告が含まれています。
バブル分析の古典
原著が出版されたのは今から34年前の1990年で、手元にある日本語訳は2021年の新版第7刷です。
英語のタイトル「A Short Histrory of Finacial Euphoria」のとおり、チューリップバブルから出版直前のブラックマンデーにいたるまで、歴史上の投機ブームを解説しています。
1991年に出た日本語版では、当時すでに崩壊が始まっていた日本のバブル景気について、コメントが追加されています。
『ウォール街のランダムウォーカー』(最新第13版)や『敗者のゲーム』(最新第8版)と同じく、版を重ねて売れ続けている投資本の古典です。
内容は一般向けの薄くて読みやすいエッセイなので、ときおり読みかえして相場の傾向や自身のバイアスをチェックするといった使い方に向いています。
投資家なら一家に一冊、枕元に常備しておきたい名著です。
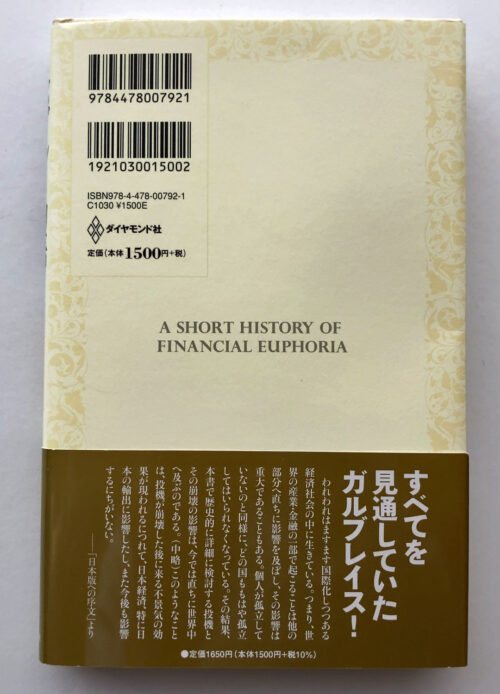
すべてを見通していたガルブレイス!
歴史上のバブル
ガルブレイスは歴史上のバブルとして、以下の事件を取り上げています。
- 1630年代…オランダのチューリップ狂
- 1720年…フランスのミシシッピ会社(ジョン・ロー)
- 1720年…イギリスのサウスシー・バブル
- 1810年代、1837年、1857年、1873年…アメリカの投機バブル
- 1920年代…フロリダの不動産バブル(チャールズ・ポンジ)
- 1929年…アメリカの大恐慌
- 1950~60年代…IOSショック(バーナード・コーンフェルド)
- 1987年…ブラックマンデー
- 1990年…日本の不動産バブル
オランダのチューリップバブルとイギリスの南海バブルについては、『ウォール街のランダム・ウォーカー』でも解説されていました。
この2つは古典的なバブル現象としてよく取り上げられるので、ご存知の方も多いと思います。
サウスシーと同時期にパリで起こっていた投機バブル、19世紀アメリカで何度も発生した投機ブームについて、自分はよく知らなかったので勉強になりました。
20世紀においても大恐慌とブラックマンデーの間に、プチバブルといえそうな投機の流行や詐欺まがいの事件が何度も起こっていたそうです。
1969年のIOS(Investors Overseas Services)なんて、覚えている人は今やほとんどいないのではないでしょうか。
「IOS」とウェブで検索しても、iPhoneのOSに関する情報しか出てきません。
執筆当時はまだ記憶に新しかったとしても、そこから20年も経つとすっかり忘れられてしまうようです。
バブルの周期は20年
本書には「金融に関する記憶は極度に短い」という有名な言葉が出てきます。
人間の仕事の諸分野のうちでも金融の世界くらい、歴史というものがひどく無視されるものはほとんどない。
一般人が歴史的事件として把握している以上に、投機バブルというのは頻繁に起こっているようです。
著者は19世紀のアメリカで何度も繰り返された投機ブームを分析して、バブルの発生周期を「20年」と推測しています。
投資家が世代交代して過去の惨事が忘れられるまで、20年という歳月は妥当なところかと思います。
しかし1929年の大恐慌はショックが大きかったので、正気でいられる期間が例外的に20年より長くなったとも説明しています。
ガルブレイスの唱える「バブル20年周期説」は根拠が薄く、過去200年くらいの歴史を振り返って得られた経験則という程度の仮説にすぎないかもしれません。
そういえば2000年のITバブル、2008年のリーマンショックからそろそろ20年…最近のNVIDIA株やビットコインの暴騰は、新たな投機バブルの徴候とという予感もします。
2020年のコロナショックは瞬間的な下落率こそ凄まじかったものの、過去のバブルに比べれば突発的な調整局面にすぎなかったと考えられます。
バブルに共通する特徴
ガルブレイスは過去の投機バブルに共通するパターンをいくつか指摘しています。
1. てこの再発見
バブルの時期、金融の世界では「車輪の再発明」ならぬ「梃子(レバレッジ)」の再発明が何度も繰り返されているそうです。
古くは「銀行が所有している現金以上に銀行券を発行できる」というアイデアから始まり、1920年代の持株会社や1980年代のM&Aも新たな信用創造のツールとして流行しました。
「少ない元手にレバレッジをかけて多額の投資ができる」という発想が、何か画期的な発明のようにもてはやされるのがバブル特有の現象とされています。
当時は斬新なテクニックに見えても、ブームが終わってみればいつもの見慣れた手口にすぎなかったというオチです。
極端な例は、ポンジ・スキームのような出資金詐欺になります。
バブルの最中、チャールズ・ポンジやマイケル・ミルケン(ジャンクボンドの推進者)のように金融上の革新をもたらした発明家は、天才と褒め称えられたそうです。
バブルの特徴…「暴落の前に天才がいる」という箴言は、本書『バブルの物語』邦訳初版の副題になっていました。
その後2008年に邦訳新版が出たときは「人々はなぜ『熱狂』を繰り返すのか」という、わかりやすい副題に変更されました。
後述のバブル関連本、『根拠なき熱狂』というベストセラーにあやかった改題と思われます。
2. 警告を歓迎しない圧力
バブルの渦中に、投機ブームの行きすぎを警告する識者がいないわけではありません。
例として19世紀イギリスの評論家ウォルター・バジョット、連邦準備制度の創設者であるポール・M・ウォーバーグ、世界恐慌を予測したロジャー・バブソンが紹介されています。
しかし群衆が投機のユーフォリア(陶酔的熱病)に支配されている間、批判的な意見は無視されるか、激しい反発を受ける傾向があります。
バブルの恩恵を受けている既得利益層への攻撃とみなされるからです。
1929年の大恐慌の前には、当時有名だった経済学者のアーヴィング・フィッシャーがロジャー・バブソンを批判して、投機を擁護する楽観的な意見を表明していました。
金融業界のしかるべき地位にある人ほど、主流派に反してバブル相場の最中に警鐘を鳴らすのは難しいのかもしれません。
ガルブレイスも1986年のブラックマンデー前夜に株価崩壊を予言しましたが、『ニューヨーク・タイムズ』に掲載を断られた経験があるそうです。
本書以外にも『大暴落1929』などバブル関連の本を多く書いているのは、経済界のマイノリティーとして不遇の時期を経てきた反動なのかもしれません。
序言でアルフレッド・マーシャルの「経済学者は喝采を受けることを何よりも恐れるべきだ」という言葉を引用していて、これはガルブレイス自身の信念なのだろうと思います。
3. 事後の反省は難しい
バブルに共通のパターンは、暴落後にも表れると指摘されています。
投機が崩壊した後は原因究明や犯人探しが行われますが、投機行為それ自体―すなわち投資家全体の過ち―という論点は出てこないそうです。
- 投機に関与した特定の個人や組織はやり玉に挙げられるが、金融業界全体が間違っていたという議論にはならない(意味がないし、誰にも歓迎されない)
- 市場はあくまで中立的かつ効率的であり、バブルの原因は市場の外にあったとみなされる(市場原理主義)
インサイダー取引やプログラム・オプション取引など「投機の手段」に規制がかけられるものの、「人々が投機に走る傾向そのもの」は反省されることがありません。
議論の的とならないのは投機それ自体、またはその背後にある異常な楽観主義である。「投機の結末では、真実はほとんど無視される」。これが最も注目すべきことなのである。
歴史的な文脈からすると、ガルブレイスは当時主流だった市場原理主義に反対の立場だったと考えられます。
市場は聖域、市場はトーテム…投機的な風潮が非難されないのは、市場に対する古典的な信仰のせいだと、厳しく批判しています。
「市場は外部的な影響を中立的かつ正確に反映する」という仮説に対し、バブルの要因は市場そのものに内在していて、市場は完全でも中立でもないというのが著者の主張です。

バブルから身を守る術
それでは投資家がどうやって相場の崩壊から身を守るかというと、「バブルの共通パターンを認識するしかない」と説明されています。
現実には、唯一の矯正策は高度の懐疑主義である。すなわち、あまりに明白な楽観ムードがあれば、それはおそらく愚かさの表れだと決めてかかるほどの懐疑主義、そしてまた、巨額な金の取得・利用・管理は知性とは無関係であると考えるほどの懐疑主義である。
ガルブレイス自身は未来予測を控えるタイプの経済学者だったようで、本書の結論もあいまいな精神論で終わっています。
逆に考えれば、「決定的な予防手段がない」というのがバブルの真の恐ろしさなのかもしれません。
著者が指摘するように、バブルの構造的要因が市場そのもの、市場に参加する人々の群集心理にあるならば、人間が投資するかぎり避けようがないと思われます。
ギャンブル依存症の人が、「自分はおかしいかもしれない」と自ら認識できるケースはまれでしょう。
歴史に学べない理由
ガルブレイスは「歴史の教訓」に学ぶことを勧めていますが、一方でそうした教訓は不明瞭だとも認めています。
アダム・スミスやJ・S・ミルなど、昔の経済学者が述べたことも、将来の指針として役に立つかどうかというと微妙です。
これを読んで、マンガ『インベスターZ』7巻の巻末特別記事を思い出しました。
経営学者の橘川武郎教授さんが、バブルの歴史について書いているコラムです。
「歴史に学べ」といわれても難しいのは、そもそも歴史が「そういうものだから」らしいです。
そのときどきによって国や経済、社会の状況(歴史的文脈=コンテクスト)が異なるので、過去から現在を100%予測することは不可能と説明されています。
金融に関する歴史的健忘症は、人々の心がけが足りないからというよりも、過去の教訓をいかすのが思ったより難しいからではないでしょうか。
経済学者のバブル分析も典型的な後講釈で、未来の予測にはほとんど使えないと素直に認めた方がよいかもしれません。
日本のバブルについて
『バブルの物語』の邦訳出版に際して、ガルブレイスは「日本版(1991年版)への序文」を追加し、日本のバブル現象に関する考察を加筆しています。
おもしろいと思ったのは、日本の場合「政府がなんとかしてくれる」という安心感がバブルの楽観的ムードを助長した、という指摘です。
アメリカでは、政府は基本的に市場の傍観者で、むしろ自由市場の敵だとみなされているそうです。
1929年、株価暴落の際も、政府ではなくモルガン財閥などニューヨークの銀行家たちに対して、市場を救済する役割が期待されていました。
結局、日本の政府もアメリカの銀行も両国のバブル崩壊を阻止することはできませんでした。
いずれは国家や大企業が尻ぬぐいしてくれるだろう(でないと彼らも困るから)という、責任回避の風潮が、投機ブームを後押ししていたのかもしれません。
バブルの成因に国民性のようなものは多少反映されていそうですが、ギャンブル好きなのは人類共通の傾向といえそうです。
行動ファイナンスへ
著者が指摘した「資本主義(自由企業制度)自体に内蔵されているバブルの種」とは一体何なのか?
「株式市場には利用可能なすべての情報が織り込まれている」という効率的市場仮説では説明できない環境的要因があると、ガルブレイスはおそらく見抜いていたのでしょう。
それを執筆時の段階では「集団的狂気」「大衆的狂気」という程度にしか説明できなかったのだと思います。
その先の研究は行動経済学に引き継がれることとなります。
株式市場を動かす心理的要因に触れた本としては、2000年に出たロバート・J・シラーの『根拠なき熱狂』が有名です。
こちらはインターネットバブルの崩壊直前に出版されたこともあって、当時はかなり話題になったそうです。
ガルブレイスが注目した陶酔的熱病という現象は、90年代以降に発展した行動ファイナンスの理論でうまく説明できると思います。
『根拠なき熱狂』によれば、人間はもともと自信過剰になりやすいバイアスを抱えていて、バブルのピークでは情報カスケードとフィードバック・ループによってその傾向が増幅される、という感じです。
『バブルの物語』では、そこまで突っ込んだ人間心理の分析は行われていませんでした。
しかし「バブルの発生は市場の外的要因だけでは説明できない」と看破した点で、先見の明があったと思います。
ガルブレイスの予言
将来また起こるであろう投機バブルに関して、ガルブレイスは以下のような言葉で締めくくっています。
こうした問いに答えはない。誰にもわからない。答えようとする人は、自らの無知がわかっていないのだ。しかし確実なことが一つある。それは、こうしたエピソードはまた生まれるだろうし、その先にはもっとあるだろう、ということである。
自分には特別な金融的洞察力がそなわっていて、バブル崩壊の直前で売り抜けられると考えていたら、それこそが無知の証拠であるという皮肉が込められています。
そして過度に楽観的なムードが市場にひろがっているとき、「良識ある人は渦中に入らない方がよい」という謙虚な態度を推奨しています。