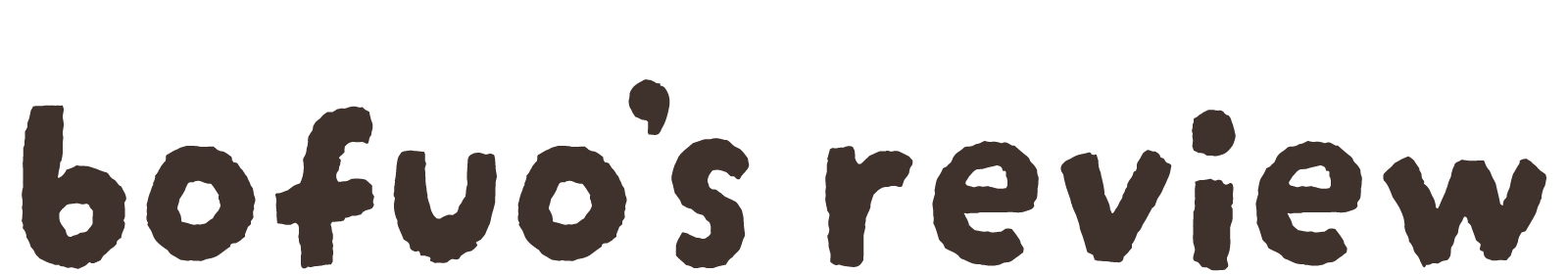本記事のリンクには広告が含まれています。
MUFGでセーフティ共済
普段はまったく使わないMUFGでも、中小機構の経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金引き落としには継続利用しています。
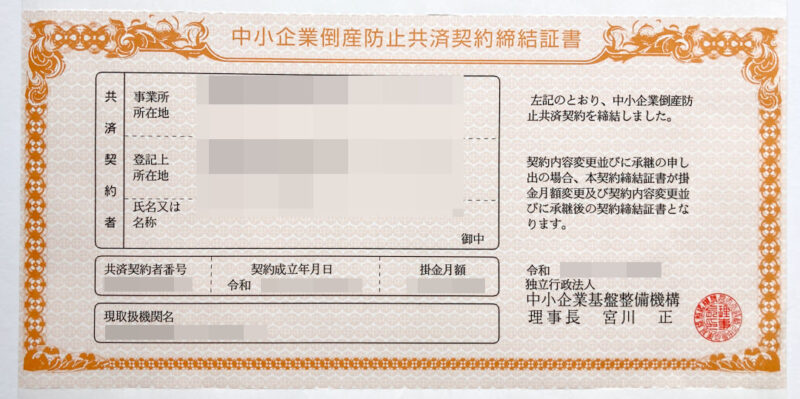
法人はネット銀行不可
節税に有効なセーフティ共済ですが、加入できる金融機関は今でも都市・地方銀行などに限られています。
最近はルールが緩和され、個人事業なら「ゆうちょ銀行、楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行」からも振替できるようになったようです。
法人の場合は「加入時のみ」GMOあおぞらネット銀行を掛金口座に設定できると案内されています。
しかしネット銀行は窓口がないせいか、加入手続きは委託団体経由で行うことになります。
所属団体が商工会であれ組合であれ、事前に加入して会費も納めなければならず、手続きが面倒です。
同じく中小機構の小規模企業共済であれば、上記3つのネット銀行を掛金引落口座に指定できるうえ、変更手続きもオンラインで可能になりました。
こちらは法人ではなく個人が対象のため、倒産防止共済の個人事業主と同じ扱いなのかもしれません。
一部はオンライン手続き可能に
2023年9月1日から経営セーフティ共済の手続きがいくつか、オンラインで申し込めるようになりました。
掛金月額の増額/減額、掛止め、再開、前納のほか、登記住所や電話番号の変更も可能です。
ただし他社や個人事業からの共済契約承継など、込み入った手続きは従来どおり窓口での手続きが必須です。
将来的にはこうした申請もオンラインで可能になり、法人の掛金振替もネット銀行で済ませられるようになるかもしれません。
それまではせっかくつくったMUFG口座を活用しようと思います。
節税条件の厳格化
小規模企業共済と同じく、節税ツールとして有益な経営セーフティ共済ですが、とうとう抜け穴をふさがれるときが来ました。
2024年10月1日以降、共済解約後2年間は、再契約しても掛金を損金算入できないという新ルールが、税制改正によって定められました。
みそぎの期間が「2年間」というのは、消費税の課税事業者選択や簡易課税制度と同じです。
このくらい時間を空ければ、あからさまな節税には使いにくいだろうという目論見でしょう。
そもそも中小機構の共済は、掛金が経費や所得税控除として認められるものの、解約後に受け取るお金は収入・所得とみなされ課税対象になります。
つまり課税タイミングの先延ばしにすぎないわけで、今回のルール変更は厳しすぎるような気もします。
普通の会社であれば、共済を活用しつつ売上・経費を適切にコントロールするのは、案外難しいものです。
場合によっては逆効果で税率アップしてしまうという、諸刃の剣ともいえる制度です。
銀行窓口での手続きも面倒なので、今後も締め付けが厳しくなるようなら、セーフティ共済の節税利用はあきらめてもよいかと考えています。
MUFGの窓口事情
ゆうちょ銀行のネットワークにはかなわないとはいえ、三菱UFJも国内の大都市圏なら支店の窓口を利用できます。
法人口座や共済の手続きなど、込み入った相談をしたいときに窓口が使えるのは、ネット銀行にないメリットといえます。
窓口が予約制に
最近は銀行窓口の混雑を緩和するためか、対面で相談するには予約が必要になっています。
特に法人口座の場合は、口座開設から住所変更、保険料や共済掛金の振替など、ほとんどの手続きが予約必須に変わっています。
そうと知らずに飛び入りで来店してしまい、受け付けてもらえなかったこともあります。
わざわざ遠方から電車で来たので、無駄足に終わってショックでした。
今はきちんと予約してから行くようにしていますが、時間を守らなければならないのは面倒です。
支店が多く、いつでもふらっと立ち寄れる郵便局(ゆうちょ銀行)に比べて、メガバンクはこの点が不利だと感じています。
とはいえ予約どおりに窓口へ伺えば、待たずに話すことができます。
相談内容もウェブ上のフォームから事前に伝えてあるので、手続きもスムーズです。
繁忙期や時間帯によって、都内の支店では数十分も待たされるのが常識でした。
窓口の予約制は一長一短ですが、長い目で見れば銀行側・顧客側、双方にメリットのある合理的なサービス改良だと思われます。
取引支店は変更不可
メガバンクの支店・ATMが地方に少ないとはいえ、近隣の大都市に出ればまだ利用できるのは救いといえます。
しかし共済関連の手続きで最寄りのMUFG支店に相談したところ、「加入した支店でしか受け付けられない」という回答でした。
経営セーフティ共済の意外な盲点ですが、同じ金融機関のなかであっても掛金振替口座は他支店に変更できません。
掛金の増減など基本的な手続きも、最初に申し込んだ支店の窓口でしかできないルールになっています。
しかも最近は支店の統廃合が進んでいるので、取引支店が消滅・移転することもありえます。
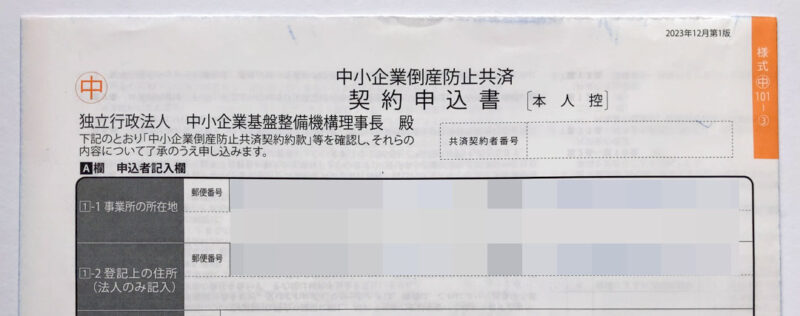
以前、首都圏内で転勤したときにこの制約に気づきました。
当時はまだ支店が近かったので、たまに電車で旧取引店に行って各種申請を済ませていました。
しかし地方に引っ越すと、わざわざ手続きのために東京まで出張するのも面倒です。
交通費や宿泊費など余計な費用もかかります。
せめて最寄りの支店に法人口座を移動できないかMUFGに電話で相談してみたところ、それでも不可との回答でした。
しぶとく窓口に行って「法人の登記住所も移転した」など事情を説明したら、ようやく他支店経由で都内の支店に書類を転送してもらえることになりました。
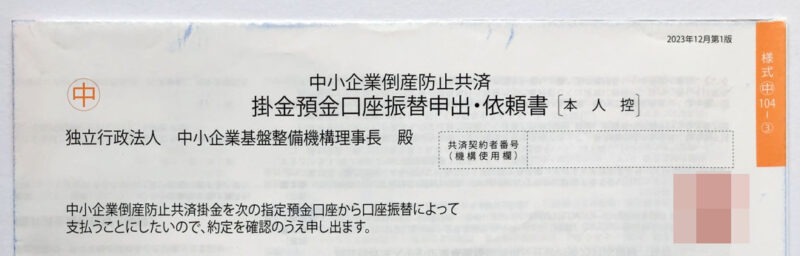
窓口での説明が毎回面倒ですが、いちおうこの特例措置によって、地方移住後も経営セーフティ共済を使えるようになっています。
法人の住所移転は不便
法人口座の支店移動ができないのは、そもそも「会社が引っ越す」というのがレアケースだからかもしれません。
業務拡大のため首都圏内でオフィスを移転するとか、地方に新たな拠点を構えるという可能性は考えられます。
しかし都内なら移動も楽ですし、地方に進出する場合も地元の支店で新たに口座をつくると思います。
わざわざ登記住所ごと他県に移すのは面倒ですし、法務局の管轄が変わると変更登記で登録免許税を6万円もとられます。
ひとり会社で引っ越しの多い場合は、都市部のバーチャルオフィスで登記しておくのもありかと思います。
中小機構の共済対策としては、移住先の地方銀行や信用金庫で法人口座を開設するのも手です。
ただし引っ越すたびに取引銀行を増やすのも面倒ですし、法人口座は個人より審査も厳しくなります。
結局のところ、今あるMUFGの口座を最大限活用して、いずれネット銀行でも掛金引落できるようになるのを待つ、というのが無難に思われます。