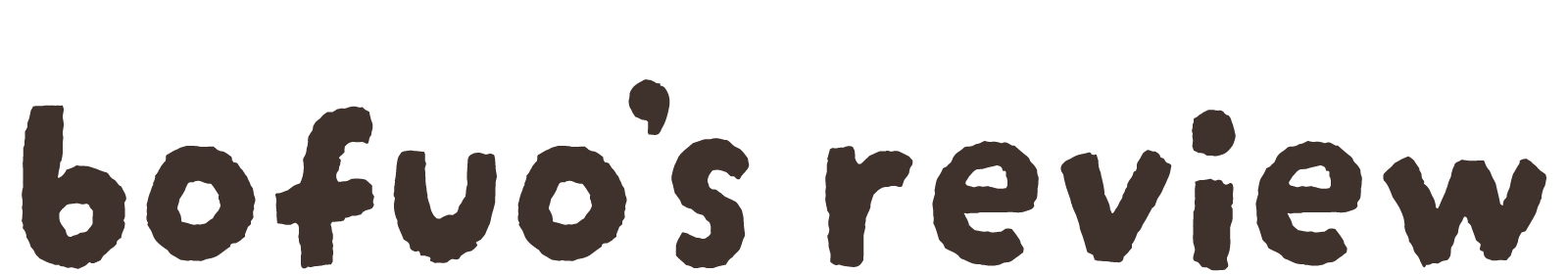新しくつくったサイトで、GoogleのAdsense審査にようやく合格できました。
何度目かの挑戦で受かった理由を考えると、YMYLコンテンツの除外が有効だったように思われます。
グーグルの方針なので仕方ないとはいえ、特定分野の記事については良識のある内容でも無視されたりペナルティーを受けるというのは理不尽に感じます。
また最近のアドセンスではOfferwallを出せたりして、ウェブ広告の表現が多様化してきているようです。
アドセンスに関連して、近年のSEOとネット広告の傾向について考えてみました。
以下は売れない古参ブロガーの恨み節といった感じの雑談です。
本記事のリンクには広告が含まれています。
YMYLは無料ブログで書く
今回アドセンスに合格できた理由は、「医療系の記事を外す」という工夫が大きかったように思います。
ほかは微々たる改良ですし、記事数もボリュームもすでに十分だった可能性があります。
すると考えられる原因は、「なんらかの違反を犯してペナルティーを受けている」ということです。
せっかく時間をかけて執筆し、思い入れもある記事ですが、しぶしぶ削除したらあっさりアドセンスに合格できました。
YMYLの語源
YMYLといえば、ヴィッキーロビン、ジョー・ドミンゲスの『お金か人生か』(原題:Your Money or Your Life)が元ネタと思われます。
英語の原著は1992年に書かれたもので、かのRDPD…『金持ち父さん 貧乏父さん』(Rich Dad Poor Dad、1997年)より若干古いです。
ちなみに似たようなジャンルの『週4時間だけ働く』(The 4-Hour Workweek、2007年)という本も、4HWWと略されることがあります。
なにかこういう財テク・リタイア系の本は、4文字アルファベットに短縮して標語化されやすい傾向があるのかもしれません。
FIRE(Financial Independence, Retire Early)というバズワードもまさにそうですね。
書籍のYMYLは個人的に好きだったのですが、2020年からグーグルのガイドラインに採用されたおかげで、別の文脈で広まってしまいました。
ちょうどこの頃、米国発のFIREムーブメントが日本でも広まりはじめた時期でもあり、『お金か人生か』という古典本が連想されやすかった背景もあるようです。
また個人的にはゲームの女神転生シリーズに出てくる唯一神、YHVHを連想します。
「みだりに名前を唱えてはならない(記事で触れてはいけない)、神(Google)の名前」という意味では、洒落が効いているように思います。
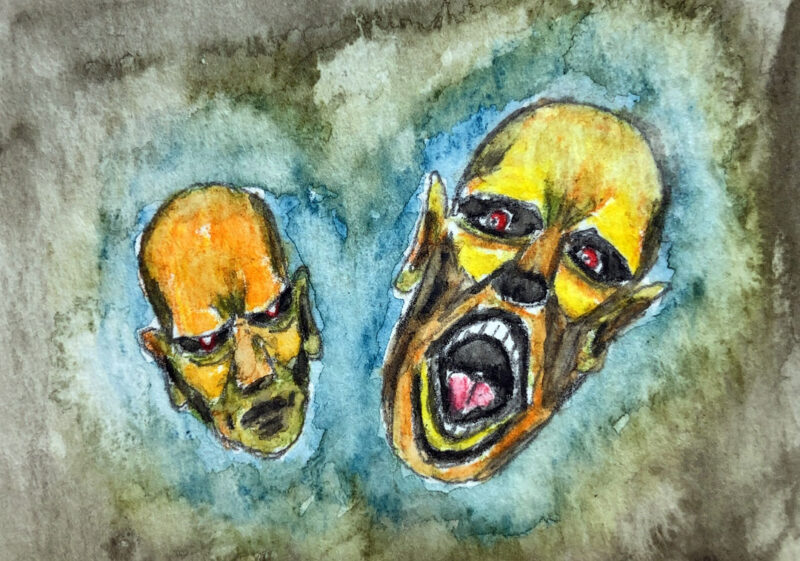
健康ネタは無理ゲー
YMYLのなかでも医療分野で個人ブロガーが活躍するのは、もう難しいでしょう。
検索上位に出るほどの権威性や信頼性(E-A-A-T)を獲得できるとしたら、よほど名の知られた専門家で、公的機関や大学などから外部リンクをもらう必要があると思います。
どんなに有益でおもしろい記事を書いたとしても、土俵にすら乗せてもらえない可能性が高いです。
数年前から病名や治療法などをグーグルで検索しても、厚生労働省や病院、製薬会社などのオフィシャルなページしか上位に出なくなりました。
「水虫やハゲ」といった下世話なテーマで検索しても、個人ブログのおもしろいネタにたどり着くことはありません。
見つかったとしても皮膚科やクリニックの営業用ブログといった、営業目的の記事ばかりです。
検閲が強化されてつまらなくなったとはいえ、怪しげな情報が出てきてうのみにする人が出てくるよりは、ましなのかもしれません。
ワクチン反対のトンデモ説や陰謀論にもエンタメ要素はありますが、グーグルとしては黙殺したほうが自社および社会の利益になると判断されたのでしょう。
こうしたパターナリズムの利点と検閲のデメリットは、どのあたりで線引きするのが有益か、議論のわかれるところだと思います。
お金の話はまだいける
YMYLの医療系は無理だとしても、金融や資産運用の話なら個人ブロガーにまだチャンスはありそうです。
「NISA 運用」といった検索語では金融庁、銀行、証券会社しか出てこないですが、「ブログ」というワードを追加すると、昔ながらの個人ブログも1ページ目にあらわれます。
以前から投資パフォーマンスの公開というのはブログの定番ネタでした。
昨年、新NISAが始まってからは、NISAの運用報告をコツコツ書く人が増えたようです。
NISAは基本的に投信積立てなので、テクニックや銘柄選択はほとんど関係ありません。
買っている商品もオルカンやS&P500のインデックスなら、運用成果も似たり寄ったりです。
これまで日陰の存在だったインデックスファンドが流行した背景には、個人のブログやSNSが一役買ったという説もあります。
手数料を削って広告も打たず、銀行や証券会社も利幅が薄いので積極的に宣伝しないという隠れた金融商品は、個人の草の根、情報発信と相性がよかったのでしょう。
これに金融庁が投資先として推奨している事情も重なり、インデックス投信がバズったように思われます。
国内の投資人口はまだ2割ほどらしくいので、新NISAが話題といっても微々たる影響にすぎません。
ただ10年前にNISAや確定拠出年金(DC、現iDeCo)をコツコツ始めたときは、今ほど多くのメディアで「インデックスファンド」という金融商品を見ることはなかったです。
グーグル八分の恐怖
あまりGoogleに批判的なことを書くと、そのこと自体、SEO的にネガティブな評価を受けてしまうかもしれません。
(反対にMicrosoftのBingには歓迎されそうです)
アドセンスの不可解な審査結果や、YMYLのペナルティーらしきものを経験すると、グーグルの隠れた方針について疑心暗鬼になってしまいます。
下手なことを書けば検索エンジンに無視される、というよりも「サイト全体がバンされてしまうのではないか」という恐怖におびえています。
アカウント凍結のおそれがある無料ブログと同様に、WordPressの独自ブログであってもグーグル八分を意識しないわけにはいきません。
ブログ全体に悪影響が及びそうなら、不穏な記事はまた取り下げて、無料ブログに移し替えようと思います。
トップページをサイト型に変えたことで、本題と関係ない裏話のような記事も盛り込めるようになったのはメリットと感じています。
読者に気づかれにくいところで、微妙な記事を出したり引っこめたりしても、たいして迷惑はかからないはずです。
もっとも、誰にも読まれず検索にもかからない話など、公開しても自己満足にしかならないとは言えますが…
無料ブログへ記事移行
YMYLに関連して自分の健康状態というのは、食レポと同じくらい素人でも書きやすい話題です。
ある程度の年齢をすぎると、日ごろの体調や健康法、通院や入院の経験談といったものが鉄板ネタになってきます。
初対面で共通の趣味もなく、政治的・宗教的バックグラウンドもわからないときに、天気のことなら無難に話せるような感じです。
こうした健康ネタをもうブログで書けないのか…と思うと寂しい気持ちになります。
しかしそもそも検索順位など気にしなければ、なんでも自由に書いて構わないはずです。
あえてWordPressでなく無料ブログを使えば、YMYLな話題や、たわいもない日記・雑記でも読んでもらえる可能性は高まります。
たとえばアメーバブログで「不整脈」や「変形性膝関節症」と検索すると、個人の闘病日記が多く出るほか、それぞれ病名のハッシュタグまで見つかります。
noteは病院や専門家の割合が多めですが、個人の治療レポートもまだ出てきます。
ためしに当サイトからYMYLな健康記事をアメブロに移したところ、短期間で予想以上のPVがつきました。
数年間WordPress上で放置したいたときよりも、反応がぜんぜん違うと感じます。

もちろん初参加のユーザはブログ上で紹介されやすかったり、ビギナーズラックが寄与しているとは思います。
しかしこれまでは検索エンジンからほとんど流入がなかったので、それに比べれば特定ブログ内での話とはいえ、執筆のモチベーションも自然とあがってきます。
グーグルの検閲が強化されるにつれて、そこから逃れた人たちが別のエコシステムに移り、住み分けが進んできているのではないでしょうか。
おもなSNSの間で、ユーザの属性や使用目的が分かれているのと似たような状況です。
ウェブメディアの多様性
たとえひとつのSNSが独占的なシェアを占めたとしても、ユーザが高齢化するにつれて、話題の合わない若年層は別のSNSを求めると思います。
機能の優劣というより顧客層の相性といった感じで、ニッチなサービスにも必ず需要はあるといえます。
かつてはパソコン向けのOSでも、Windowsに比べてmacOSやLinuxは利用者が少ないため、ウイルス感染の標的になりにくいといった話もありました。
ビジネスの持続可能性を意識すると、使用するプラットフォームにも多様性をもたせたほうが安全といった考え方もできます。
もう20年前の流行だったmixiやSecond Lifeがいまだに存在して、しかも一部の人たちの間で盛り上がっているという理由もうなずけます。
近年Twitterの運営方針に反発して、mixiに移ったユーザ層がいるそうです。
Second Lifeも時代を先取りしすぎたメタバースですが、枯れたメディアにこだわるマニアックな人たちも存在するものです。
時代遅れのサービスでも、ユーザのコミュニティーに根強く支持される場合の思考実験としては、テッド・チャンの『ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル』というSF小説が参考になります。
ハヤカワ文庫SFの『息吹』という短編集に収録されている作品です。
こちらはロボット型アバターの育成に関するフィクションですが、SNSやメディアプラットフォームの栄枯盛衰にも通ずる要素があります。
はてなブログやアメブロも、テッド・チャンの描いた「ディジエント」のように、ユーザ主体で細々と維持されていくような気がします。
noteやWordPressなど競合サービスの失敗・衰退によっては、意外とまた盛り上がることがあるかもしれません。
近頃フィルムカメラや編み物が若者の間でブームになっているように、レトロな日記ブログが将来また流行る可能性もゼロではないと思います。